〉Vol.5 どうしたら学校へ行けるかという思いがあった頃(この記事です)
「不登校は、本人の心の叫びを表した結果。小さい頃からずっと疑問を抱き、納得いかないことをさせられてきた結果だと思うので、早く気づかされてよかったと思います」と語る琴子さん。そこにはいったいどんなドラマがあったのか。琥博くんとのこれまでと、これからについて、乳児期からたどってお伺いしたお話を、連載でお届けします。
スクールカウンセラーと対話してみた11月
2年生になり、保健室に行くことや症状が増えた琥博くん。
必死の訴えで学童やスイミングを辞め、学校に行くこともできなくなってきていました。
11月7日からは、琴子さんが仕事の間、琥博くんは、しばらく琴子さんの実家で過ごすことにしました。

学校へは、毎朝、登校しない旨の連絡を入れていました。
その時は教頭先生も親身になって話をしてくれていました。
スクールカウンセラーに会うことも勧められました。
11月中旬にはじめてスクールカウンセラーとお話をしましたが、ヒントも変化も得られなかったのが実際でした。
反対に、先生方に説明したことを二重に説明しなければならなかった状況から、教師との連携をとっているのではないのだということにも気づかされました。

「学校イヤ!ゼロ分もイヤ!」
11月下旬。琥博くんから、「学校イヤ!ゼロ分もイヤ!」という言葉。
しかし、何がイヤなのか、ということはわかりませんでした。
この当時は、どうしたら学校に行けるかという思いがあったので、先生方と話し合い、先生に迎えにきてもらうことを試みることになりました。
最初は教頭先生と担任の先生二人がきて、和むような話題や、興味をそそるような話し方で話をするうちに、「行ってみようか?」といったかんじで先生と歩いて行っていました。
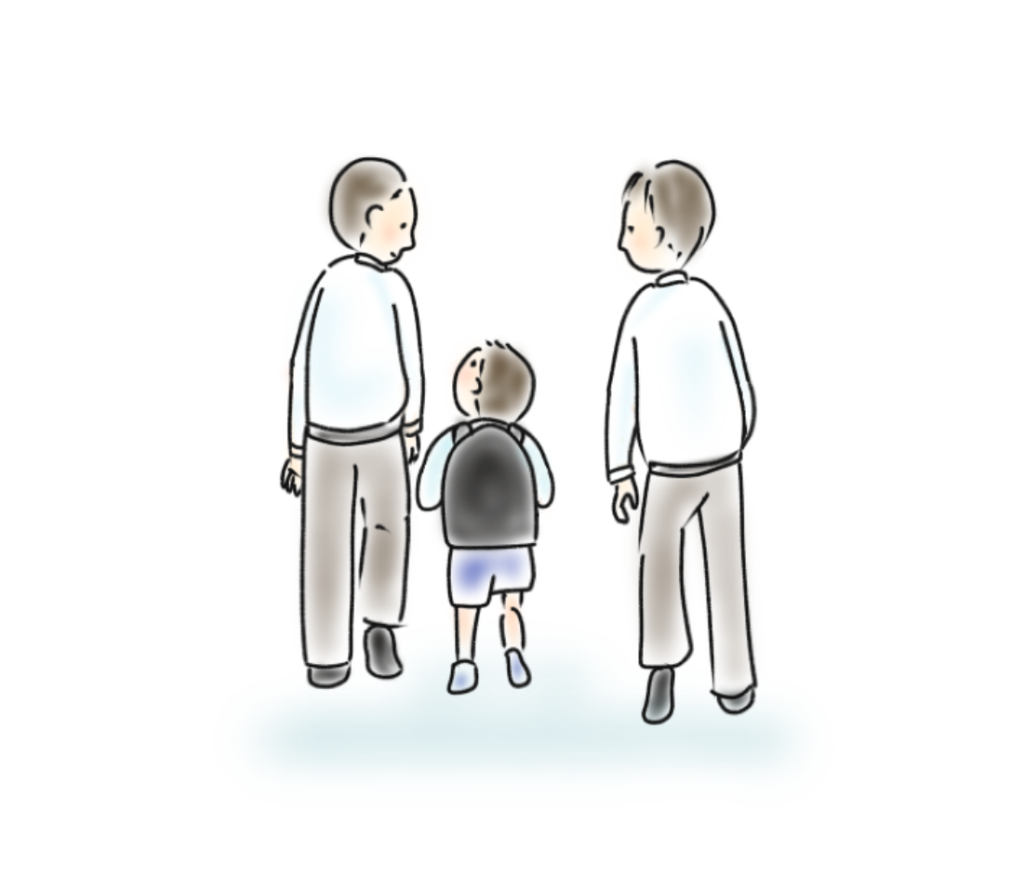
教頭先生「琥博くんは、話をすることが楽しいようだから、担任とだけではなく、話し相手になる先生が関わっていくようにします」
琴子さんは、このまま行けるようになるのかなと、漠然と思っていました。
しかし、この状態が2週間くらい続きましたが、琥博くんは教室には行けておらず、保健室や職員室で過ごしていました。

次に、お友達のお母さんから連絡がきて、「息子が迎えに行ったら行けるかな」と協力を申し出てくれました。
その息子さんは、琥博くんの、保育園からの好きなお友達なので、迎えにきてくれたら行きました。
しかし、それも3回目くらいでイヤと言って部屋から出なくなりました。
12月14日のこと。
琥博くんは、その日を境にずっと行けなくなりました。
つづく
解説「HSCと不登校」
子どもは学校に行くもの。それは私たち親にとって、当たり前で普通のことすぎて、子どもが普通に適応してくれなければ困ってしまいます。
子どもから「学校に行きたくない」と言われても、どうして行きたくないのか、何がそんなにイヤなのかがわかりません。
子どもに聞いてもわからないことが多いもの。
子ども自身、どうして学校がイヤだ、行きたくない、と思うのか、うまく言葉にできません。
下記のような『HSCに多い、学校に適応しにくい特徴』を見てみると、どうしてうまく言葉にできないのか、HSCにとって何がつらいのか、理解の助けになるのではないでしょうか。
●HSCに多い、学校に適応しにくい17の特徴
※斎藤 裕医師作成
① 集団に合わせることよりも、自分のペースで思索・行動することを好みます。
② 観察される、評価される、急かされる、競争させられることなどを嫌う傾向にあります。
③ 外向型の子どもたち向けにつくられている学校で、求められることを苦手に感じることが多く、人と比較したり、うまくいかなかったりした場合に自信を失いがちです。
④ 人の集まる場所や騒がしいところが苦手です。誰かの大声や、誰かが怒鳴る声を耳にする、誰かが叱られているシーンを目にするだけでつらいと言います。
⑤ 1対1で話をするのを好みます。大勢の前で発表をすることや、大勢の人と会話をすることが苦手な傾向にあります。
⑥ 親友がクラスの中に1人でもいると安心ですが、クラス替えで親友と離れなければならなくなったりすると、すごく落ち込んだりします。
⑦ 物事を始める、人の輪に加わるなどの行動を起こすのにも時間がかかります。これは目の前の状況をじっくりと観察し、情報を深く処理(大丈夫かどうか確認)してから行動するためです。
⑧ 刺激を受けすぎてそれに圧倒されると、落ち着きがなくなる、話を聞けなくなる、物事がうまくできなくなるといった状態になりやすいです。恥ずかしさや刺激が多すぎて不安を感じる状況や環境では、冷静さや自制心を失って、その子が持っている本来の良さや力が発揮できなくなるのです。
⑨ 想定外のことや突発的な出来事に対してパニックになってしまうことがあります。
⑩ 自分と他人との間を隔てる「境界」が薄いことが多く、他人のネガティブな気持ちや感情の影響を受けやすい傾向にあります。例えば、他人の気分に影響されて動揺したり、悲しくなって元気がなくなったりするなど。
⑪ 安心できていない人に、急に話しかけられる、頭をなでられる、顔や体を触られる、抱きつかれたりすることを嫌がります。
⑫ 嫌だと思ってもなかなか「No」が言えません。支配的な人や、あなたのためになると言って受け入れさせるような関わり方をしてくる人には特にです。
⑬ 先生がどのような人かの影響は大きいです。相性が良くない場合は地獄だと言います。
⑭ 子ども扱いする人や権威を示す人、権力をふりかざす人が極端に苦手です。
⑮ 自分の気質に合わないことに対して、ストレス反応(様々な形での行動や症状としての反応)が出やすい傾向にあります。例えば「落ち着きがなくなる」「固まる」「泣きやすい」「言葉遣いや態度が乱暴になる」「引きこもる」、「不眠」「発熱」「頭痛」「吐き気」「腹痛」「じんましん」など。
⑯ 細かいことに気がついたり、ささいな刺激に敏感に反応したり、過剰に刺激や情報を受け止めたりするため、学校での環境や人間関係から強い「ストレス」を感じてしまい、不適応を起こしやすいところがあります。
⑰人のささいな言葉や態度に傷つきやすく、小さな出来事でも「トラウマ」となりやすいところがあります。
※⑮⑯⑰に関しては、親子の愛着関係に傷が入り、愛着の土台が不安定になっている場合、ストレスやトラウマに対して、すでに脆弱になっているケースが見られます。
大人は少なくとも自分で職場を選ぶことができます。
そしてどうしても嫌なら辞めて、ほかの職場に替えることができます。
ですが、今の学校教育システムの中では、子どもは自分に合っていると思う学校を選べません。
自分に合った先生も選べません。
これがやりたい、これについてもっと深く知りたいと思う科目も選べません。
選択肢がないのです。
子どもに備わっている特性は、認知、行動、情報処理、社会性などの面において多様です。
しかし、日本では子どもの多様性よりも、すべての子どもたちに同じ教育を与えることが平等である、という意識が強い傾向にあります。
そのため、学校では、子どものそれぞれの特性に関係なく、画一的な内容と方法で教育が行われているというのが現状です。
それはある子どもにとっては適したものであっても、ある子どもにとっては適さないということも十分に起こり得ることなのです。
このことが、HSCたちの心の健康を奪い、人生に残念な影響を与えてしまっているのではないか。
そのような視点を持つことの重要性を強く感じています。
HSCの気質の特徴に示したように、学校環境や現行の教育システムは、HSCの気質に合ったものと言えるものではなく、それらに対して不適応を起こしても何ら不思議ではありません。
HSCにとって、「学校に行けないこと」「学校に行きたくないこと」は、
①気質に合わないことによる拒否反応である
②本来の気質の特性が活かされないまま、本当はやりたくないことをやらされることが多く、自分のペースで「自発的」に「主体性」をもって自分らしく生きることができなくなった結果である
と考えることが大切です。
特に②の場合は、「外向性に価値を置く社会性」や「その子にとっての過剰な適応能力」を求められた結果、「期待に応えようと頑張ってきたことに対する息切れ」や「集団のペースに合わせて生きることへの限界」を意味しているものではないかと考えています。
『HSCを守りたい』p.73-77より引用

