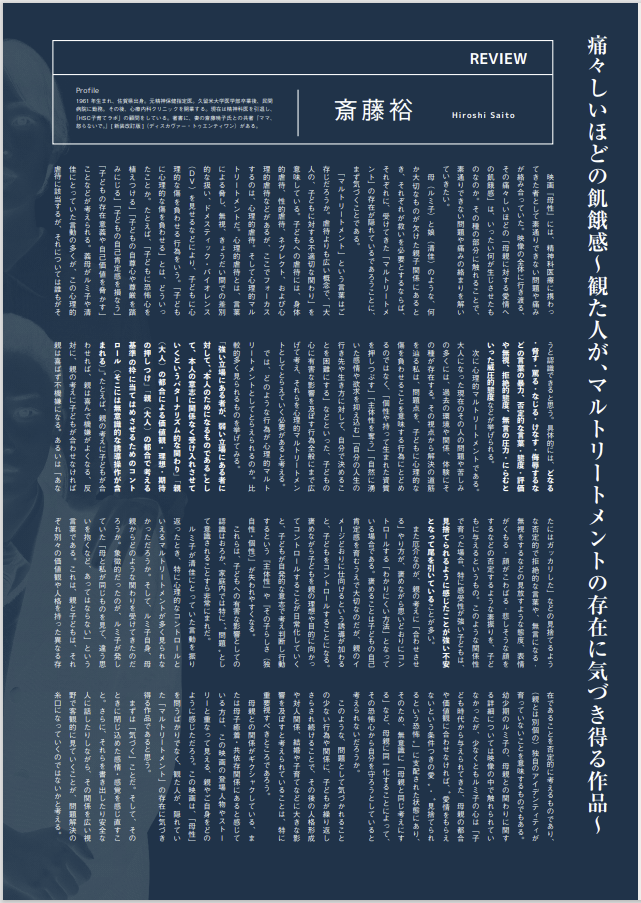2022年11月23日に公開された、映画『母性』。
2012年に発表された湊かなえさんの小説『母性』が、戸田恵梨香さん・永野芽郁さん出演で実写映画化され、話題になりました。
その映画『母性』のパンフレットに掲載されるレビューの寄稿依頼をいただいたのが同年8月。
『ママ、怒らないで。(新装改訂版)』をお読みくださった編集者さんがご推薦くださったとのことで、共著者である夫とともにお声がけいただきました。
映画『母性』は、出演されている俳優の方々の演技力が圧巻で、その演技力と映画の構成に混乱しつつ、映像の全体を覆いつくす“いびつさ”が、心理カウンセラーとしての自分に何かを訴えかけてくるような作品でした。
私は、いびつさは何なのか。何がそうさせるのか。その背景にあるものは何なのか。一度観ただけでは拾えない。すごくそう思いました。
そして、それぞれの感情の機微を逃さないよう一言一句、表情や動きをかみしめながら、再度、再々度と入り込みました。
さて、映画公開と同時に発売となったパンフレットですが、表紙をはじめ、インパクトが強く、様々な角度から映画『母性』の深みに触れられる、大変見ごたえのある素敵な1冊でした。
私ども夫婦のレビューは見開き1ページに並べて掲載していただいてます。
夫のレビューについてですが、映画と限られた文字数のおかげで1ページに凝縮させることができた大変重要な視点や知識、メッセージを、クライアントさんや、HPを訪れる方々に、ぜひ全文読んでいただきたいと思うことが多々あります。
今回、このHPに全文引用させていただく許可を得ることができましたので、下記に掲載いたします。
映画『母性』パンフレット掲載 寄稿レビュー (執筆:斎藤 裕)
痛々しいほどの飢餓感
~観た人が、マルトリートメントの存在に気づき得る作品~
映画『母性』には、精神科医療に携わってきた者として素通りできない問題や痛みが絡み合っていた。
映像の全体に行き渡る、その痛々しいほどの「母親に対する愛情への飢餓感」は、いったい何が生じさせたものなのか。
その種の部分に触れることで、素通りできない問題や痛みの絡まりを解いていきたい。
母(ルミ子)と娘(清佳)のような、何か大切なものが欠けた親子関係にあるとき、それぞれが救いを必要とするならば、それぞれに、受けてきた「マルトリートメント」の存在が隠れているであろうことに、まず気づくことである。
「マルトリートメント」という言葉はご存知だろうか。
虐待よりも広い概念で、「大人の、子どもに対する不適切な関わり」を意味している。子どもへの虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、および心理的虐待などがあるが、ここでフォーカスするのは、心理的虐待。そして心理的マルトリートメントだ。
心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な扱い、ドメスティック・バイオレンス(DV)を見せるなどにより、子どもに心理的な傷を負わせる行為をいう。
「子どもに心理的な傷を負わせる」とは、どういったことか。
たとえば、「子どもに恐怖心を植えつける」「子どもの自尊心や尊厳を踏みにじる」「子どもの自己肯定感を損なう」「子どもの存在意義や自己価値を脅かす」ことなどが考えられる。
義母がルミ子や清佳にとっていた言動の多くが、この心理的虐待に該当するが、それについては誰もがそうと認識できると思う。具体的には、
どなる・脅す・罵る・なじる・けなす・侮辱するなどの言葉の暴力、否定的な言葉・態度・評価や無視、拒絶的態度、無言の圧力・にらむといった威圧的態度などが挙げられる。
次に心理的マルトリートメントである。
大人になった現在のその人の問題や苦しみの多くには、過去の環境や関係、体験にその種が存在する。
その視点から解決の道筋を辿る私は、問題点を、子どもに心理的な傷を負わせることを意味する行為にとどめるのではなく、「個性や持って生まれた資質を押しつぶす」「主体性を奪う」「自然に湧いた感情や欲求を抑え込む」「自分の人生の行き先や生き方に対して、自分で決めることを困難にする」などといった、子どもの心に有害な影響を及ぼす行為全般にまで広げて考え、それらを心理的マルトリートメントとしてとらえていく必要があると考える。
では、どのような行為が、心理的マルトリートメントとしてとらえられるのか。比較的多く見られるものを挙げてみる。
「強い立場にある者が、弱い立場にある者に対して、“本人のためになるものである”として、本人の意志に関係なく受け入れさせていくというパターナリズム的な関わり」
「親(大人)の都合による価値観・理想・期待の押しつけ」
「親(大人)の都合で考える基準の枠に当てはめさせるためのコントロール(そこには無意識的な誘導操作が含まれる)」。
たとえば、親の考えに子どもが合わせれば、親は喜んで機嫌がよくなる、反対に、親の考えに子どもが合わせなければ親は喜ばず不機嫌になる。
あるいは、「あなたにはガッカリした」などの見捨てるような否定的で拒絶的な言葉や、無言になる・無視をするなどの見放すような態度、表情がくもる・顔がこわばる・悲しそうな顔をするなどの否定するような素振りを、子どもに与えるというもの。
このような関係性で育った場合、特に感受性が強い子どもは、見捨てられるように感じたことが強い不安となって尾を引いていることが多い。
また厄介なのが、親の考えに「合わせさせる」やり方が、褒めながら思いどおりにコントロールする「わかりにくい方法」となっている場合である。
褒めることは子どもの自己肯定感を育むうえで大切なのだが、親のイメージどおりに仕向けるという誘導が加わると、子どもをコントロールすることになる。
褒めながら子どもを親の理想や目的に向かってコントロールすることが日常化していくと、子どもが自発的な意志で考え判断し行動するという『主体性』や『その子らしさ(独自性・個性)』が失われやすくなる。
これらは、子どもへの有害な影響としての認識はおろか、家庭内では特に、“問題”として意識されることすら非常にまれだ。
ルミ子が清佳にとっていた言動を振り返ったとき、特に心理的なコントロールといえるマルトリートメントが多く見られなかっただろうか。
そして、ルミ子自身、母親からどのような関わりを受けてきたのだろうか。象徴的だったのが、ルミ子が発していた「母と私が同じものを見て、違う思いを抱くなど、あってはならない」という言葉である。これは、親と子どもは、それぞれ別々の価値観や人格を持った異なる存在であることを否定的に考えるものであり、(親とは別個の)独自のアイデンティティが育っていないことを意味するものでもある。
幼少期のルミ子の、母親との関わりに関する詳細については映像の中で触れられていなかったが、少なくともルミ子の心は「子ども時代から与えられてきた、母親の都合や価値観に合わせなければ、“愛情をもらえないという条件つきの愛”・“見捨てられるという恐怖”」に支配された状態にあり、そのため、無意識に「母親と同じ考えにする」など、母親に同一化することによって、その恐怖心から自分を守ろうとしていると考えられないだろうか。
このような、問題として気づかれることの少ない行為や関係に、子どもが繰り返しさらされ続けることで、その後の人格形成や対人関係、結婚や子育てなどに大きな影響を及ぼすと考えられていることは、特に重要視すべきところであろう。
母親との関係がギクシャクしている、または母子癒着・共依存関係にあると感じている方は、この映画の登場人物やストーリーと重なって見える、親やご自身をどのように感じただろう。
この映画は、「母性」を問うばかりでなく、観た人が、隠れていた「マルトリートメント」の存在に気づき得る作品であると思う。
まずは「気づく」ことだ。そして、そのときに閉じ込めた感情・感覚を感じ直すこと。さらに、それらを書き出したり安全な人に話したりしながら、その関係を広い視野で客観的に見ていくことが、問題解決の糸口になっていくのではないかと考える。
医師 斎藤 裕
出典:2022年11月23日公開 映画『母性』パンフレット掲載 寄稿レビュー