金木犀の香りが漂い始めた9月20日の東京。
小学生の息子と一緒に向かったのは、東大駒場キャンパスの101号館。
哲学の、梶谷真司(かじたに しんじ)先生のオフィスでした。
今回は梶谷先生を紹介していただいた、ライターの栃尾江美さんも、お子さん2人連れでインタビューに同行してくださいました。
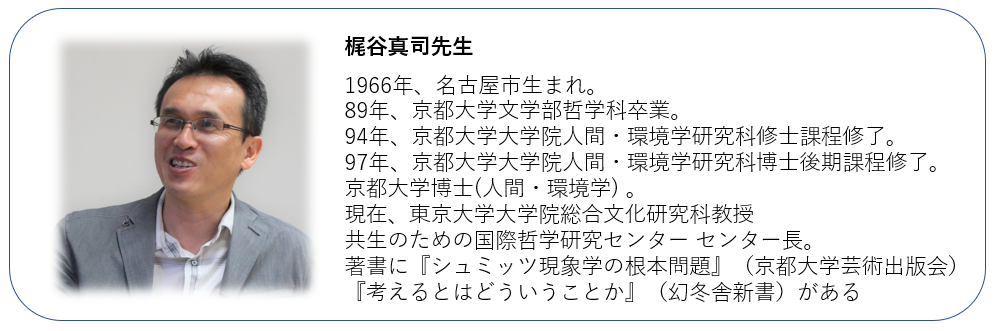
梶谷先生にお伺いしたいこと
お会いする前に、梶谷先生が寄稿されたという記事「考える自由のない国―哲学対話を通して見える日本の課題」を拝読して、とても感銘を受けました。
学校という空間では、「何でも言っていい」ということが徹底して否定されている。
学校で子どもたちは、正しいこと、いいこと、先生の意向に沿うことを言うように訓練される。
間違ったことを言えば「違う」と言われ、悪いことを言えば怒られ、先生の意に添わなければ嫌われる。
もちろん正しいこと、良いことを教えるのは必要である。
人の気に入ることが何かを学ぶのも重要だろう。けれどもだからといって、それ以外を排除していいわけではない。
とても思い当たりがあるわけです。
学校に限らず、生まれ育つ私たちをかたち作る環境が、そのまま言い表されていると感じたのでした。
このように、思考の自由を奪う教育についてのご意見をお持ちの梶谷先生。
シリーズでお届けする、このインタビューの目的は、学校に行かない選択をする親子にとっての安心材料を見出してくこと。
まずは、大学院の教授、哲学の先生である梶谷先生には、教育現場の専門家という視点で、学校に行きたくないという子どもたちを取り囲む教育環境、そして子育てや将来についてお話をお伺いしたいと思います。

学校に行けなくなった時の受け止め方で
 kokokaku
kokokaku梶谷先生、よろしくお願いします。
今日は、学校に行きたくない、行けないという子やその親御さんのことを中心にお話をお伺いしたいと思います。
今私はHSCという敏感な気質の子が、ほぼ5人に1人はいて、そのすべてではありませんが、気質が学校に合わないことが多く、不登校の原因のひとつになっているということを伝えるための活動をしています。
この夏休み明けに学校に行けなくなったという子も多くてですね。
 梶谷先生
梶谷先生必ずしもHSCというのではなくても、色々あって学校に行けなくなったりすることも多いでしょうね。
しかしどのような原因であっても、親の受け止め方次第で子供は随分楽になるでしょう。子供が何か問題があったとしても、親がそれを問題だと思っていなければ、外ではいろいろ言われても、まあいいんだと思って生きていけるかもしれない。
だけど親が過剰に反応して、例えば世間体を気にしたりとか、「あんたのせいで恥をかいた」みたいな感じでいると、子供にとっては大したことがないのに、苦しくもなりますよね。
 kokokaku
kokokakuそれはありますね。親の期待に応えられないのは、子どもにとってとてもつらい。でも身体が動かない…
一方で、親が「学校へ行かせなければ」という気持ちから離れた時期から子どもの側がとても楽になったというのはよく聞きます。
質問をしないのをよしとする文化
 梶谷先生
梶谷先生
たとえば、東大生ってやっぱり勉強していい成績を取ることで評価されてきた子がすごく多いんです。
そうすると優秀じゃなきゃいけないというプレッシャーがすごく強くて、わからないと言えないとか、質問しないというふうになります。
あとは自分ができるって思えなかったり、人から評価されないような場には極力身を置かないようにしているように思います。
 kokokaku
kokokaku
東大生ではないですけど、聞けないというのはすごくありました。
質問って難しいですよね。
 梶谷先生
梶谷先生何言っても何聞いてもいいという場を作ると、 みんなそれなりに適応して、それなりに意見を言えるようにはなるんだけど、質問というのはなかなか出てこないんです。
質問って難しいんですよ。
なかなか思いつかないのもあるし、たぶん「聞いていい」という感覚がないんです。
自分が恥をかくかもしれないとか、相手に不快な思いをさせるかもしれないかもというのがあって。
普段の生活の中で、「なんでそんなこと言っているの?」って質問したら、怒っているように見えたりするし、聞かれた方は責められたのかと思うじゃないですか。
だからみんな質問ってしないんですよ。
あとは相手の言っていることがわからなかった時に、「今のはどういう意味ですか?」と聞くと、馬鹿じゃないかとか、恥ずかしい思いをするんじゃないかと思うので、みんな聞かないんです。
 kokokaku
kokokakuたしかに、ネガティブな結果を誘発しそうなイメージが先行しますね。
質問して注目されるのもなんだか気が引けますし。
 梶谷先生
梶谷先生普段から質問をしないのをよしとする文化というのはやっぱり、学校ですよね。
学校でそういう考え方を本当に「植え付けられる」と言ってもいいくらいです。
質問を歓迎する先生ってあまりいないですから。
 kokokaku
kokokaku質問の種類によって授業での質問はいいけれども、
例えば「何で運動会に出ないといけないんですか」とか。
 梶谷先生
梶谷先生(笑)それは絶対ダメですね。授業でも、許されている質問というのは、当たり前のことかもしれないけど、授業に関係したことですよね。
関係ないことを質問すると怒られるじゃないですか。

 kokokaku
kokokakuそうですよね、本当に適応しないといけないですよね。
 梶谷先生
梶谷先生質問していいことって非常に限られているから、みんなそれが何かをすごく考えるか、そもそも質問しないという選択肢をとるんです。よほど先生の顔色を読める子で、頭のそこそこいい子じゃないと、質問ってできないですよ。
 kokokaku
kokokaku何だか息が詰まりますね。
質問してはいけない文化というのは、原因があってそうなっているんですよね。
 梶谷先生
梶谷先生生徒の疑問に答えるということは、おそらく学校教育の目的ではないんだと思うんです。
習ったことがわからないということだけではなくて、もっと言うと、子どもが知りたいことに答えるのは教育の役割ではないんですね、学校では。
普通に考えたら知りたいことを学ばせる、それをサポートする、教えるというのが広い意味での教育なんだけど、学校教育はそうなっていない。
日本では一斉教育でカリキュラムが選べないですよね。 試験を受けて自分がそこをわかっていたら次に進みたいとか、自分のペースで進めたいと思ってたという話もけっこう聞きます。 子どもは勉強するペースも、どうやって勉強するかも、どこで何を勉強するかも決められないじゃないですか。 全部与えられたものを飲み込むのか拒否するか、ぐらいですもんね。 選択や判断の権利が与えられていないですね。 それがとてもつまらなかったという話を聞くのですね そもそもテストで点数をつけて評価する必要すらないかもしれないじゃないですか。 私はそう思うタイプです。 ある塾で小テストをやめたら点数が伸びたという例があるんですよね。 テストって勉強をつまらなくしていくだけの面がある。 もちろんテストがあったら、とにかく闇雲に頑張る子もいますけどね。 誰のためのテストかと言うと評価のためで、評価は誰のために何のためにやっているかと言うと、学校のためなのかな。 先生のためというのですらない気がします。 学校という制度そのものが序列化を要求するので、成績評価をしなければならず、先生はその中で役割を果たしているだけ。 では先生が序列化したいのかと言うと、必ずしもしたいわけじゃないかもしれません。 そうなんですよね。 制度自体が序列化させるもので、先生ではたしかにない。 だから色んな理由があると思うのですが、勉強しては評価され、君はできる、君はできないって序列化される。だから学校がつまらなかったという方は多いですよね。 はい。いろんな要因が重なって学校に行きたくない、友達と合わないとか、勉強についていけないとか、授業がつまらないとか、先生と合わないとか、あると思うんですけど、つまらなくなって学校に行きたくないと言う感覚というのも自然なことのように感じてます。 学校はつまらないから行きたくないというのは、正常な感覚だと思います。 授業が面白いから学校に行きたいという子は少数派だと思うんです。 友達がいるとか部活が楽しいとか、勉強以外の理由で学校に行く。 でも、学校って基本はやっぱり授業じゃないですか。一番多くの時間を割いているわけですから。 授業がどうでもいい学校でいいはずがないわけです。 勉強がどうでもいいんだったら、ただの遊びの場にすればいいわけですよ。 (笑)学校が遊び場だったらつまらなくはないですよね。 学校に行きたくないといった子が、例えば家でどういう風に過ごせば大丈夫なんだろうというイメージがわかないのでみんな不安なんですよね。 実際に子供が学校に行かないとなると、なかなか大変ですよね。 じゃあ勉強どうするのってなるじゃないですか。家でやるにしても、親では対応しきれない。 でも学校の授業を変えないといけないって、誰も言わないんですよ。 授業が面白くなれば、学校行くでしょう。 学ぶって元来面白いものだと思うんです。 だって自分が興味を持って、これやりたいと思ったら、 別に勉強できない子でも、そういうことは熱心にやって、できるようになっていくじゃないですか。 でも子供が興味を持ったことをサポートする、という感じにはなかなかならない。 やっぱり、社会的にこれが良いとされるものをやんなさいと言って、習い事でも「楽しいでしょ」って言われて、半ば強制されてやっていたりするように思います。 学校に行きたくないと言う子に傾向的に多いのは、これが好きという興味の幅が狭かったり、深かったり、決してまんべんなくやりたいというのではない、という気持ちがしっかりあるからそうなってるのかなって… 東大生に「君たちは嫌なことでも頑張ってやれる変わった子たちだよね」と言うんです。 そうでなければ、ここまできてないです。 好きなことだけやって東大まで来られるわけじゃない。 東大にたくさん入れる学校がいい学校で、東大に子供を入れると立派な親、みたいな価値観が根強くあります。 だけどそれは、嫌いな事をいっぱいさせた学校であり親だったということでもあると思うんです。 中には何でもすぐできちゃうような、びっくりするくらい頭の良い子もいますけど、ほんの数パーセントじゃないですか? いい大学を出ていい企業に入って、そうしとかないと子供が苦労するんじゃないかという心配が根強いと思うんです。
僕はときどき学生たちをからかって、「君たちバカだと思われるくらいなら死んだほうがマシと思っているでしょ?」って言うんです。 それで反発してくると思って言ったんですよ。 だけど真顔で、 「先生、実はそうなんです。どうしたらいいですか」と涙目で訴えてくる子もいました。 あぁ、それは、苦しいのですね
苦しいんですよ。 自分を守らなきゃいけない。守る術というのは彼らにとって頭がいいということなんです。 他に色々あるのかもしれないし、そもそもそんなに守らなくてもいいのに、彼らにはそれが一番大事だから、とにかくそこを死守しないといけない。 そこが崩れたら自分がもうダメになるというぐらいに思っている子もいるんです。 だから東大に「東大までの人」という表現があるみたいなんですが、東大に来たら、自分より頭がいい人がいくらでもいる。 みんなから「頭がいい」と言われていた自分が、ただの凡人になるのが受けられなくって折れてしまう子がいるんです。 スポーツでもそうですよね。 俺はできると思って、強豪校に入ったらもっと強いやつがいて、自分は所詮この程度だったと。 そういう場合、そういう自分とうまく折り合いをつけていければいいんだけど、それができない子もいるわけです。 できると思っていた自分の実力のレベルが思ったほどでもなかったと知るのはつらいですよね。
だから東大の子がいつも自信満々で、傷ついてないかと言うと、そうでもないんです。 それに褒められて育ってきているので、褒め続けられなければいやみたいなところがあります。 例えば何かやったら「すごいね」とか、先生から「よく頑張った」とか、授業中の質問も「いい質問だね」と言われたい。 そう言ってもらえる確信が持てなければ、発言しないようなところがあります。彼らはもちろんある意味「勝ち組」なんだけど、今の世の中で、勝ち組ですら幸せではない。苦しんでいるんです。 幸せとはいったいなんだろうって…。どういう生き方をしても、その場面というのは出てくると思うんですよね。 今おっしゃったように、勝ち組でも決して幸せかどうかと言うとそうではないと。
「勝ち組」の人は、そうやって苦しんで、今の自分の仕事とか幸せを掴んできてるので、幸せになるのに苦しまなくてはいけないと思っているんでしょう。 そうすると世の中のシステムというのは、人が苦しむようなシステムしか作らないわけですよ。 この苦しみによって自分はここに来たと思っている。 苦しみを経ない限りはここに来られないようなシステムを本気でいいと思っている。 自分たちのように苦しんでここまで来る子たちを再生産するようなシステムを作って、その苦しみに耐えられない人間を上に上がってこられないようにするわけです。 世の中のいろんなシステムを考えるのって、そういう勝ち組の頭のいい人たちですから。 苦しみに耐えられないままだと、何やってもうまくいかないぞって、頭の中で声がしてそうな時もあります。 学校の話で、例えば学校がつまんないのが当たり前の反応だとおっしゃってて、他にもいろんな理由があって行かない選択をしたら、そっちの方が今は幸せだとは思うんですけど、一般的には、母親としては職業が一番心配なんじゃないかなと。 お金に心配なく暮らしていけるかどうかということが心配なのではないかと。 そういうのについてはという風にお考えですか? まず「お金に困らない」ということが何なのか、ということですが、 例えば僕は結婚した時、大学院生で収入があまりなかったんですけど、大学院生だし、哲学だし、仕事あるの?ってもともと思っていたので、あまり気にしなかったです。 大学院生になるということは、就職しないということです。 定職に就かず、アルバイトなどをしながらの生活だったので、財布にはいつも少しのお金しか入っていなかったけど、苦しいとは思わなかった。 将来どうなるかということもご自身では不安に思われなかったと・・・ でもやりたいことを諦めて定職に就いてこんなはずじゃないと思うより、自分で行きたい道を選んで、裕福でなくてもやりたいことをやっていった方が良いというのはありますよね。 だから、お金に困るとか、苦しいという感覚ではなかったのか・・・。 親の理想や心配と、子の感覚や望んで選ぶ生き方は同じとは限らないですね。
親の反応を見て子どもって感じ方を決めていくので、親が心配症なら子どもも心配症になるという部分があるでしょうから、親の影響は多かれ少なかれあるでしょう。 子どもが学校に適応していなかったとしても、親が「まぁいいんじゃない」って受け止めるのか、「あなたそんなことで将来どうするの?」と言って対するのでは、やっぱりその後の子どもはずいぶん変わってくるんだろうと思うんです。 子どもがもともともっている素質もあるでしょうけど。 受け止め方という点で、HSCというのは気質の概念なんですけど、それがわからないから反応を見て否定してしまうんですね。 その子にとっては自然な反応なんですけど、それに対して周りが否定的に反応してしまうということが起こるので。 でも、敏感で、例えばびっくりしすぎるとか、感情反応が強いことに対して、早めにそれがわかっておけば、 「どうしてそんなにびっくりするの、そんなにびっくりすることじゃないじゃない」って言わずにすむとか。
やっぱりわかっているのとわかってないのとでは違いますよね。 誰しも最初は「普通はそうじゃない」というところから見るじゃないですか。 「他の家の子は違うのに」とか、「自分はこうじゃなかった」と思えば、やっぱり何で?ってなるでしょう。 でも、学校の先生にせよ親にせよ、結局は“大きなお世話”なんですよ、たぶん。 子どもが大騒ぎしたからって問題かというと、実際にはさほど問題ではないわけです。問題だと騒ぐから問題になるだけです。それをあーだこーだと言っても、子どもからしてみれば大きなお世話でしょう。 子どもが自分の置かれている状況を理解した上でなら、全部お前のせいだよということではなくて、ちゃんと子供に判断を委ねる部分がないと。 その上で子供が助けを求めているなら助けてあげればいいし。 別に自分でやれると言うのであればやってみればということですよね。 それで失敗したなら失敗した、それならそれでいいってこともあるので、見守るのは難しいですよね。 見守るのは・・・ですね。これは変えさせられましたね。 子供が転ぶ時に「あっ」と言っちゃうじゃないですか。1歳前後でしたけど。 これをすごく嫌がるんですよ(笑) 自分のやることに対して親が過剰反応することに対する抵抗がすごく大きくて。 うわぁ、意思が強いなって。
斎藤さんのお子さんは、小さい頃からやっぱり“大きなお世話”と思っていたんですね。 そうですね(笑) 大きなお世話に対する反発心というのが小さい頃から備わってるわけで。 それなら実は芯が強い子なんですね。 今でもちょっとでも私がずれたことを言うと見抜いて怒りますね。 適当に聞き流すと本当に嫌がります。(笑) 先生が出版される「考えるとはどういうことか」(9月28日刊行で、取材を行った9月21日はまだ発売前でした)という本の「はじめに」をWebサイトで少し拝読しました。 そこには0歳から100歳までの哲学ということで、どうして0歳かという理由が書かれていたところを拝読したのですが、 親に哲学的なものを投げかける存在と書かれてあったところに、これは本当にそうだなと思ったのです。 確かに赤ちゃんが生まれるか生まれないかで、あまりにも世界が違うと思うんですよね。 全く考えもしなかったこと、感じなかったことを考えたり感じたりするようになるから不思議だなと。
なりますよね。子どもには世の中のルールが通用しないじゃないですか。 だから、今まで自分はこうしてきたから、これで出来ていたのが、必ずしもそうならない。 剥ぎ取られるような感じで。 こんなに何もできない人だったんだと思うことが何度もあったんですよ。 子どもができる前はできていたことができない、なかった問題がでてくる、それが苦しい人はやっぱりつらいですよね。 はい。苦しい時があってたくさん内面と向き合わされた経験があるから、0歳からの哲学の意味がとてもフィットしました。 それに苦しい時に対話で救われたこともたくさんありますので、『哲学対話』というものに興味があります。 私の場合はオンライン同士ということになると思いますが。 どうでしょう。できるんじゃないですか? 本を読ませていただいて、ぜひ取り入れてみたいと思います。 今日は本当にありがとうございました。 梶谷先生とのお話を通して気づいたことは、 “何だか人はいつも何かをコントロールしようとするものだな” ということでした。 子ども、仕事、お金、将来・・・。人並み以上に良くしたいという気持ちが自分たちを動かしているのかもしれないと。 例えば学校へ行けなくなる子どもは、コントロールに疲弊する私たち大人や社会に、幸せとは何か、どう生きるのか、 といった “哲学的”な問い を投げかける存在なのかもしれないと思いました。 先生へのインタビューの最中、子どもたち3人は、静かに話をしていることもあれば、大きな音をたてたり、キャスターつきの椅子に1人をのせて、室内を回ったりしていました。 取材に子ども連れ…ふつうはあまり想像できないことですが、梶谷先生のイベントのお知らせにはどれも、「子連れ大歓迎」とあります。 だからといって託児があるわけではなく、うるさかろうが走り回ろうがただそれだけ。何か問題ある?と、先生は笑顔でお話されます。 そのようなお考えに、子どもを育てる親としては、安心と心の余白が与えられるのを感じました。 (取材・編集:斎藤 暁子kokokaku / 撮影協力:栃尾 江美さん) 【9月28日刊行の梶谷真司先生の本はこちらです。】 【クラウドファンディング・ネクストゴール挑戦中】 HSCの認知・理解の輪が広がるよう 応援よろしくお願いいたします。 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku学校がつまらないので行きたくないというのは正常だと思う
 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku
学校に行かない選択の先は?
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku勝ち組だと幸せか
 梶谷先生
梶谷先生
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生幸せになるのに苦しまなくてはいけない?
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku学校に行かない選択で親が心配すること
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生
 kokokaku
kokokaku大きなお世話
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生
 梶谷先生
梶谷先生見守る
 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku『考えるとはどういうことか』
 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokaku 梶谷先生
梶谷先生 kokokaku
kokokakuさいごに



